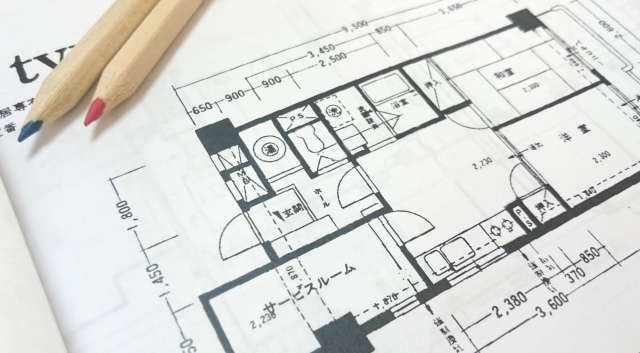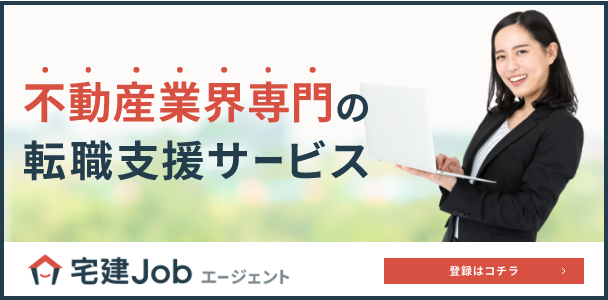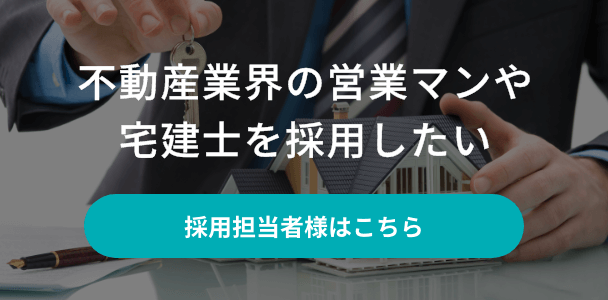昨今、アパートの建築が激増しています。
この記事をご覧の方は、土地活用や不動産投資などでアパートの建築をご検討中の方が多いと思います。アパートを建築して部屋を貸し出せば、多くの家賃収入が得られる可能性があるので魅力的ですよね。
しかし、始めたいと思っていても、
・アパートの建築はどのように進めれば良いのか
・どれくらいお金がかかるものなのか
・建築はどこに頼めばいいのか
など、分からないことだらけというのが正直なところではないですか。
そこでこの記事では、アパートを建築するにあたっておさえておきたい基本的な知識について徹底的に解説しました。この記事を読めば、アパート建築の全体像がつかめると同時に、アパート建築で失敗しないために何をすればいいのかがしっかり見えてくるでしょう。
さらに、アパートをできるだけ安く建築するために知っておきたいことについても書きました。なるべく低予算で建てたいという方のニーズにも応えていきます。
目次
0.アパート建築の流れを確認
まず、アパート建築の流れを確認しておきましょう。アパートの建築は、以下のように進められます。
②建築費用を調達する(ローンの融資を受ける)
③建築会社を選ぶ
④どんなアパートを建てるかプランを決める
⑤工事の準備
⑥着工
(⑦入居者の募集)
⑧建物完成
かかる期間はアパートの規模によって異なりますが、目安としては建てようとするアパートの階数+2~3ヶ月かかるといわれています。
以下、それぞれについて詳しく書いていきます。
1.土地を選ぶ
まず、アパートを建てるための土地を選びます。すでに土地を持っている場合はこの手順は不要です。
どのようにして土地を探せば良いかについては、どうやって探せばいいの?土地の探し方完全マニュアルに詳しい記載がありますので、あわせて参考にしてください。なお、記事はマイホーム(一軒家)を建てるための土地の探し方について記載していますが、リンク箇所はアパートを建てるための土地を探す場合もそのまま使える方法です。
2.建築費用を調達する
続いて、建築費用を調達します。
2-1.アパート建築にかかる費用
まず、アパート建築にかかる費用はどのようなものがあるか確認しましょう。
①土地購入費用
まず、上で選んだ土地を購入する費用がかかります。すでに土地を持っている場合はこの費用はかかりません。
②建築費用
次に、アパートを建てる建築費用がかかります。具体的には、以下の表のような内訳になります。
| 項目 | 内容 |
| 本体工事費 | 本体工事費 設備費 など |
| 別途工事費 | 屋外電気・給排水・ガス工事などの工事費 |
| 付帯工事費 | 外構(駐車場設備など)工事費 地盤改良工事費 太陽光発電システム設置工事費 など |
建築費用がどれくらいかかるかについては後ほど「9.できるだけ安くアパートを建築するために」で詳しく解説します。
③その他諸費用
その他諸費用としては、以下の表のようなものがかかります。
| 項目 | 内容 |
| 税金 | 売買契約書に貼る印紙税 登録免許税 固定資産税・都市計画税精算金 不動産取得税 |
| 司法書士に払うお金 (不動産登記を司法書士に依頼した場合) | 登記依頼の費用 |
| 保険料 (保険に入った場合) | 火災保険料 地震保険料 賃貸住宅費用補償保険料 |
| 銀行に払うお金 (銀行から融資を受ける場合) | 金銭消費貸借契約書に貼る印紙税 融資事務手数料 ローンの保証料 |
| 不動産仲介会社に支払うお金 (不動産仲介会社を利用した場合) | 不動産仲介手数料 |
これらの諸費用は、物件価格の10%ほどかかります。
2-2.ローンについて
アパートを建築するには上記の費用がかかりますが、全額を用意できない場合がほとんどだと思います。
そこで、足りない分についてはローンで融資を受けることになります。
アパートを建築する際に利用できるローンは、アパートローンと住宅ローンになります。
「え、住宅ローンが使えるの?」と思った方もいるかもしれません。実は、アパートの一室を自分の居住として利用する場合、住宅ローンが利用できるのです。
アパートを建築する時に使えるローンについては、頭金0円でもはじめられる?アパート経営に必要な資金の話に詳しい記載がありますので、そちらをあわせて参考にしてください。
3.建築会社(工務店)を選ぶ
続いて、アパートの建築を任せる建築会社(工務店)を選ぶことになります。
建築会社(工務店)を選ぶ時のポイントは、大きく以下の2点になります。
②信憑性のある数字を出してくるか
3-1.建築会社の提示するプランが自分に合っているか
まず、建築会社の提示するプランが自分に合っているかが重要になります。これは、下で書く「4.どんなアパートを建てるかプランを決める」と合わせて確認しましょう。
大手を除けば、建築会社によって得意分野・不得意分野があるのが普通です。具体的には、木造を建てるのが得意な会社もあれば軽量鉄骨造を建てるのが得意な会社もあります。また、単身向けの部屋を作るのが得意な会社もあればファミリー向けの部屋を作るのが得意な会社もあるのです。
そして、建築会社は自分の得意分野に基づいてプランを出してくることが考えられます。そのプランと自分の考えるプランが一致するかどうかが、重要なポイントです。
3-2.根拠のある数字を出してくるか
また、きちんと根拠のある数字を出してくるかというのも重要なポイントです。これは、建築費用の見積もりや利回り(アパート経営における収支)に関する数字について言えることです。
お金に関することで疑問がわいたら、すぐ質問してみるようにしましょう。そこで、その数字を出した根拠をきちんと具体的に説明してくれる建築会社を選ぶべきです。
ちなみに、アパート経営の正しい利回りの計算方法については、アパート経営の利回りの真実|間違った計算をしていませんか?に詳しい記載がありますので、そちらもあわせて参考にしてください。
4.どんなアパートを建てるかプランを決める
建築会社を選びながら、どんなアパートを建てるかのプランを決めましょう。
4-1.ファミリー向けか単身向けか
まず、ファミリー向けにするか単身向けにするかという点です。これは、立地から賃貸需要を考えて決めます。
例えば、近くに学校(小学校、中学校がある)がある、近くに公園があって緑が多い、といった立地であれば、ファミリー層からの賃貸需要が高いことが予想されます。
一方、大きな駅から比較的近い立地であれば単身サラリーマンの需要が高いことが予想されますし、近くに大学のキャンパスがあれば大学生の一人暮らしの賃貸需要が高いでしょう。
賃貸需要については建築会社(工務店)も調査しているはずですので、アドバイスをもらうようにしましょう。
4-2.構造について
また、構造をどうするかという点も決めなければなりません。
一般的にアパートでよく使われるのは、木造、プレハブ造、軽量鉄骨造などです。より防音性を高めたいといった場合は、鉄筋コンクリート造(RC)にすることも考えられますが、その分建築費用がかかってしまいます。
ちなみに、耐震性については、木造よりも鉄筋コンクリート造の方が優れているかといえば必ずしもそうとはいえません。木造でも地震に耐える建築技術を持った建築会社はたくさんあります。
5.工事の準備
プランを決めたら、工事の準備に取りかかります。
具体的には、敷地・構造・設備などの内容を記載した建築確認申請書を公共団体(都道府県)市区町村、又は指定確認検査機関へ提出し、確認検査員の確認を受けます。この手続きは建築会社が行う場合が多いです。
また、安全祈願の意味で、地鎮祭も行います。
6.着工
ここまで済ませると、いよいよ着工です。
着工にあたって、近隣の方々に建築工事の概要を説明しておきましょう。少なからず迷惑をかけることになるため、あらかじめ理解を得ておくのが工事をスムーズに進めるために大切になってきます。
また、工事中事故の原因になりそうなものについてはきちんと注意の表示をするなど、安全に努めましょう。
建物が完成する頃になると、上棟式という工事の無事を祈る儀式を行います。
7.入居者を募集する
上棟式を済ませると、不動産会社との間で入居者募集の段取りを決めることになります。
8.建物完成
建物が完成した後の流れは以下の通りです。
①建築検査
工事責任者から建物に関するすべての報告を受け、一緒に全部チェックします。不明点や疑問点、少しでも気になった点はかならず確認しておきましょう。
②落成式
落成式という、建物の完成を祝う式を行います(行わない場合もあります)。
建築関係者の方々の労をねぎらうと共に、近隣の方々に完成の発表を行います。
③最終報告
工事監理者から、工事監理の最終的な報告を受けます。
④引渡し
保証書類と共に、建物の引渡しを受けます。この時、アフターサービスについても確認しておきましょう。
9.できるだけ安くアパートを建築するために
以上までで、アパート建築の流れを説明してきました。
ところで、アパートを建てるとき、できるだけ安く建てたいと思うのが普通ですよね。
また、自分が見積もりを立てたときに、本当にこれが最適の値段なのか、必要以上にお金を取られていないか心配になりませんか。
そこで最後に、できるだけ安くアパートを建築するために知っておきたい、アパート建築にかかるお金についてまとめました。ぜひ参考にしてください。
9-1.建築費はどのように決まっているか
まず、建築費がどのように決まっているのかという点から確認していきましょう。
建築費は、以下の計算で求められます。
建築費=坪単価×延べ床面積
9-1-1.坪単価
坪単価とは、建物の床面積1坪あたりの費用のことです。
坪単価は、アパートの構造によって異なります。構造ごとの坪単価をまとめると、以下の表のようになります。
| 構造 | 坪単価 |
| 木造 | 40万円~60万円 |
| 鉄骨造(S造) (軽量鉄骨、重量鉄骨) | 50万円~80万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 70万円~100万円 |
9-1-2.延べ床面積
延べ床面積とは、建物の床全体の面積のことです。
例えば、2階建てのアパートの各階の床面積が50㎡であれば、延べ床面積は「50㎡×2階=100㎡」となります。
正確な延べ床面積は最終的な設計図ができるまで分かりません。ただ、延べ床面積は建ぺい率からある程度推測することができます。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建ぺい率の上限は、用途地域によって定められています。つまり、土地の区分によってその土地にどのくらいの面積のアパートを建てて良いかが決まっているのです。
| 用途地域 | 建ぺい率(%) |
| 第一種低層住居専用地域 | 30・40・50・60 |
| 第二種低層住居専用地域 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | |
| 第一種住居地域 | 60 |
| 第二種住居地域 | |
| 準住居地域 | |
| 近隣商業地域 | 80 |
| 商業地域 | |
| 準工業地域 | 60 |
| 工業地域 |
自分の土地がどの用途地域にあてはまるかは、各市区町村のHPで確認することができます。
例えば、「第二種住居地域」にある100㎡の土地に2階建てのアパートを建てる場合、延べ床面積の上限は
100(㎡)×60(%)×2(階)=120㎡
となります。
「第二種住居地域」にある100㎡の土地に2階建ての木造アパート(坪単価60万円とする)を建てる場合、かかる建築費は以下のようになります。建築費
=60万円×(100(㎡)×60(%)×2階)
=7200万円
ここで紹介した数字はあくまで参考ですが、見積もりを立ててもらって明らかにこれより高い建築費を提示されたら、少し疑ってみた方がいいかもしれません。
9-2.より安く建てられるのは工務店かハウスメーカーか
アパートを建てる時、工務店に依頼するかハウスメーカーに依頼するかで悩まれる方もいると思います。「安く建てる」という観点で考えた場合、どちらが安く建てられるのでしょうか。
結論からいうと、工務店の方が、建築に関係のない費用がかからない分若干安くなりやすいです。ハウスメーカーの場合、下請け工務店の利ざや、広告宣伝費、サービス費用(家賃保証など)を含めて建築費を算出しますので、少したかめになります。
ただ、アフターサービスのことを考えるとハウスメーカーの方が工務店より保護が厚いなど、建築費以外にも考慮すべき要素がありますので注意しましょう。
以下、それぞれのメリットを表にまとめましたので、建築会社選びの参考にしてください。
| 工務店 | ・建築費が安い ・エリアに適したプランに強い |
| ハウスメーカー | ・アフターサービスが良い ・材料や設備の質が良い ・有名なハウスメーカーであれば、融資を受ける際に有利になることがある |
10.まとめ
アパート建築に必要な知識についてまとめましたがいかがでしたか。
この記事が、アパートを建築したいとお考えのすべての方の参考になれば幸いです。